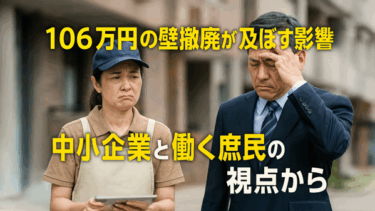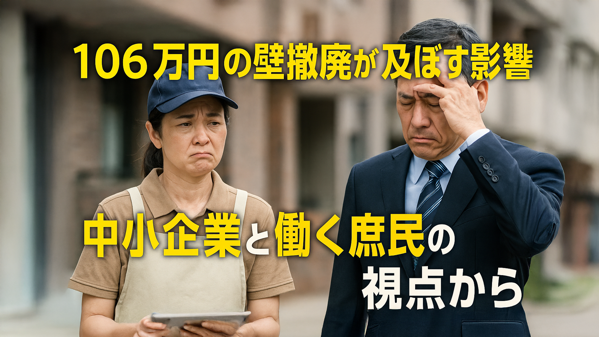年収106万円の壁撤廃が閣議決定されましたが、103万円の壁との関係性が整理されていない状況での実施によって、特にパート労働者や中小企業に様々な影響が予想されます。具体的な影響と課題を詳しく解説します。
最後に図解入りの詳しい説明PDFファイルをダウンロードできるようになっていますのでご利用下さい。
この記事の内容は動画でもわかりやすく説明しています。視覚的に理解したい方はぜひご覧ください。
▶️ 動画を見る
政府決定の背景と意図
今回の年金改革法案で106万円の壁を撤廃する主な意図は以下の通りです:
- 年金制度の持続可能性向上: より多くの人を厚生年金に加入させることで保険料収入を増やし、制度の安定化を図る
- 働き方改革の促進: 年収による働き控えをなくし、労働力不足の解消を目指す
- 将来の低年金問題への対策: パート労働者の将来の年金額増加を図る
しかし、この決定は103万円の壁(所得税)との整合性や、手取り減少の対策が十分に考慮されないまま進められた側面があります。
106万円の壁撤廃による手取り減少の具体例
ケーススタディ:パート主婦Aさん(40代)の場合
〈現在の状況〉
- 時給1,100円、週20時間、月80時間勤務
- 月収:88,000円(年収約106万円)
- 社会保険:未加入(扶養内)
- 所得税:非課税(103万円以下)
- 手取り年収:約106万円
〈106万円の壁撤廃後〉
- 同じ勤務時間・時給の場合
- 月収:88,000円(年収約106万円)
- 厚生年金保険料:約8,052円/月(労働者負担分)
- 健康保険料:約5,113円/月(40歳以上・労働者負担分)
- 年間社会保険料負担:約158,000円
- 手取り年収:約90万円(▲16万円)
図表1:106万円の壁撤廃による手取り減少のイメージ
| 項目 | 改革前 | 改革後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 年収 | 106万円 | 106万円 | 0 |
| 厚生年金保険料 | 0円 | 9.7万円 | ▲9.7万円 |
| 健康保険料 | 0円 | 6.1万円 | ▲6.1万円 |
| 手取り年収 | 106万円 | 90万円 | ▲16万円 |
※40歳以上の場合(介護保険料込み)
図表2:年収別の手取り変化のシミュレーション
| 年収 | 現在の手取り | 改革後の手取り | 減少額 | 減少率 |
|---|---|---|---|---|
| 80万円 | 80万円 | 68万円 | 12万円 | 15% |
| 100万円 | 100万円 | 85万円 | 15万円 | 15% |
| 106万円 | 106万円 | 90万円 | 16万円 | 15% |
| 120万円 | 120万円 | 102万円 | 18万円 | 15% |
| 150万円 | 150万円 | 128万円 | 22万円 | 15% |
| 160万円 | 158万円 | 136万円 | 22万円 | 14% |
※160万円以上は所得税も発生するため、減少率は変動します
103万円の壁と106万円の壁の不整合がもたらす問題
図表3:2つの壁の改革の現状と課題
| 壁の種類 | 改革内容 | 実施時期 | 課題 |
|---|---|---|---|
| 103万円の壁 (所得税) |
160万円に引き上げ | 2025年1月~ | 所得税は軽減されるが 社会保険料の負担は軽減されない |
| 106万円の壁 (厚生年金) |
完全撤廃 | 2026年10月~ | 社会保険料負担が発生し 手取りが大きく減少 |
| 130万円の壁 (健康保険) |
変更なし | – | 配偶者の扶養から外れると 国民健康保険料の負担が発生 |
働く人のケース別影響分析
ケース1:扶養内パート労働者(配偶者あり)
扶養内でパート勤務をしている主婦・主夫で、年収を106万円程度に抑えていた場合:
- 同じ勤務時間でも手取りが約15%減少
- 同じ手取りを維持するには約18%の労働時間増加が必要
- 配偶者控除は103万円の壁に関連するため、106万円の壁撤廃だけでは扶養のメリットは継続
ケース2:単身パート労働者
配偶者がいない単身者で、年収を106万円程度に抑えていた場合:
| 項目 | 改革前 | 改革後 |
|---|---|---|
| 社会保険の種類 |
国民健康保険
(全額自己負担)
|
健康保険(会社負担あり)
(労使折半)
|
| 年金の種類 |
国民年金
(全額自己負担)
|
国民年金+厚生年金
(労使折半)
|
| 保険料負担額 |
年約16万円
(全額自己負担)
|
年約16万円
(労働者負担分のみ)
※実質的には企業側も同額負担
|
| 将来の年金額 |
少ない
(基礎年金のみ)
|
増加
(基礎年金+厚生年金)
※加入期間に応じて増加
|
| 医療保険のメリット |
|
|
単身者の場合、国民健康保険・国民年金から社会保険に切り替わることで、保険料の総額は増えても労働者負担分は同程度か減少する可能性があります。また、将来の年金額増加というメリットがあります。
ケース3:学生アルバイト
学生アルバイトで年収106万円を超える場合:
- 社会保険料負担が発生し手取りが減少
- 親の扶養から外れる可能性も生じる
- 将来の年金には有利だが、学業期間中の収入減が問題
中小企業への影響と負担
図表4:中小企業の負担増シミュレーション
| 項目 | 改革前 | 改革後 | 増加 |
|---|---|---|---|
| パート従業員数 | 20人 | 20人 | – |
| 106万円未満のパート数 | 15人 | 15人 | – |
| 社会保険加入者数 | 5人 | 20人 | 15人増 |
| 年間社会保険料負担増 (企業負担分のみ) |
– | 約236万円 | 236万円増 |
| 社会保険事務負担 | 小 | 大 | 増加 |
※従業員50人の中小企業、1人あたり企業負担を年間約15.8万円として計算
※本資料は106万円の壁撤廃の影響について視覚的に理解するための参考資料です。
中小企業への支援策と課題
政府は以下の支援策を用意していますが、十分とは言えない側面があります:
- 保険料の企業負担増への支援:
- 支援策の課題:
– 年収156万円未満のパート従業員に対し、企業が3年間多く負担した場合、全額支援
– しかし、支援期間が限定的(3年間)であり、その後は企業負担が通常化
– 時限的な措置のため長期的な負担増への対応が不十分
– 事務負担の増加に対する支援が少ない
– 小規模事業者ほど影響が大きいが、規模に応じた支援の差がない
106万円の壁撤廃の懸念点と対策案
1. 手取り減少対策の不足
- 問題点:
- 対策案:
- 社会保険料負担が発生することで、同じ労働時間では手取りが15%程度減少
- 特に低賃金労働者にとって重大な影響がある
- 一定収入以下の労働者への社会保険料減免措置の導入
- 時限的でない継続的な支援制度の構築
- 最低賃金の引き上げと連動した制度設計
2. 103万円の壁との不整合
- 問題点:
- 対策案:
- 103万円の壁(所得税)は160万円に引き上げられるが、106万円の壁は撤廃
- 社会保険料負担による手取り減少を所得税の軽減だけでは補えない
- 両方の壁の改革時期の一致
- 社会保険料と所得税を総合的に考慮した負担軽減策の導入
3. 中小企業の負担
- 問題点:
- 対策案:
- 社会保険料の企業負担増
- 事務負担の増加
- 時限的な支援だけでは不十分
- 中小企業への支援期間の延長
- 従業員規模に応じた段階的な支援体制の構築
- 社会保険料の企業負担割合の見直し(一定期間)
106万円の壁撤廃の決定に潜む意図
政府が103万円の壁との関係性や手取り減少の対策が十分でないまま106万円の壁撤廃を決定した背景には、以下のような意図が考えられます:
- 年金財政の安定化優先:
- 労働力不足への対応:
- 将来の低年金問題への対処:
- 制度改革の段階的実施:
– より多くの労働者を厚生年金に加入させ、保険料収入を増やすことで財政基盤を強化
– 少子高齢化による年金制度の持続可能性への懸念
– 働き控えをなくし、労働参加率を高めることで、人手不足解消を目指す
- 経済政策として、労働市場の活性化を優先
– 非正規労働者の将来の低年金リスクを軽減
– 年金制度全体の持続可能性確保
– すべての課題を同時に解決するのではなく、まず構造的な「壁」を撤廃し、その後の調整を図る意図
働く人のためにできる対応
パート労働者の場合
- 労働時間の見直し:
- キャリアアップの検討:
- 家計全体の見直し:
- 手取りを維持するために必要な労働時間・収入を試算する
– 週20時間未満に抑えることで社会保険加入を回避する選択肢も検討
- パートから正社員への転換や、スキルアップによる時給増を検討
- 限定的な時間の中での効率的な収入確保を目指す
– 世帯全体での収入・支出のバランスを再検討
– 配偶者の扶養に入るメリット・デメリットを再計算
中小企業の場合:
- 支援制度の活用:
- 人事制度の見直し:
- 長期的な経営計画の見直し:
- 政府の支援策を最大限に活用する(保険料負担増への支援など)
- 社会保険事務の効率化・外部委託の検討
- パート従業員の賃金体系の見直し
- 労働生産性向上による人件費効率化
– 3年後の支援終了を見据えた経営計画の策定
– 必要に応じた価格転嫁や事業構造の見直し
まとめ
年収106万円の壁撤廃は、年金制度の持続可能性や働き方改革の観点からは前進と言えますが、働く個人や中小企業に大きな負担を強いる側面があります。特に、103万円の壁との不整合や手取り減少対策の不足は、庶民の立場からみれば大きな課題です。
政府には、これらの課題に対する補完的な対策の早急な検討が求められます。一方、当事者である働く個人や中小企業は、制度変更による影響を正確に把握し、自らの状況に合った対応策を検討することが重要です。