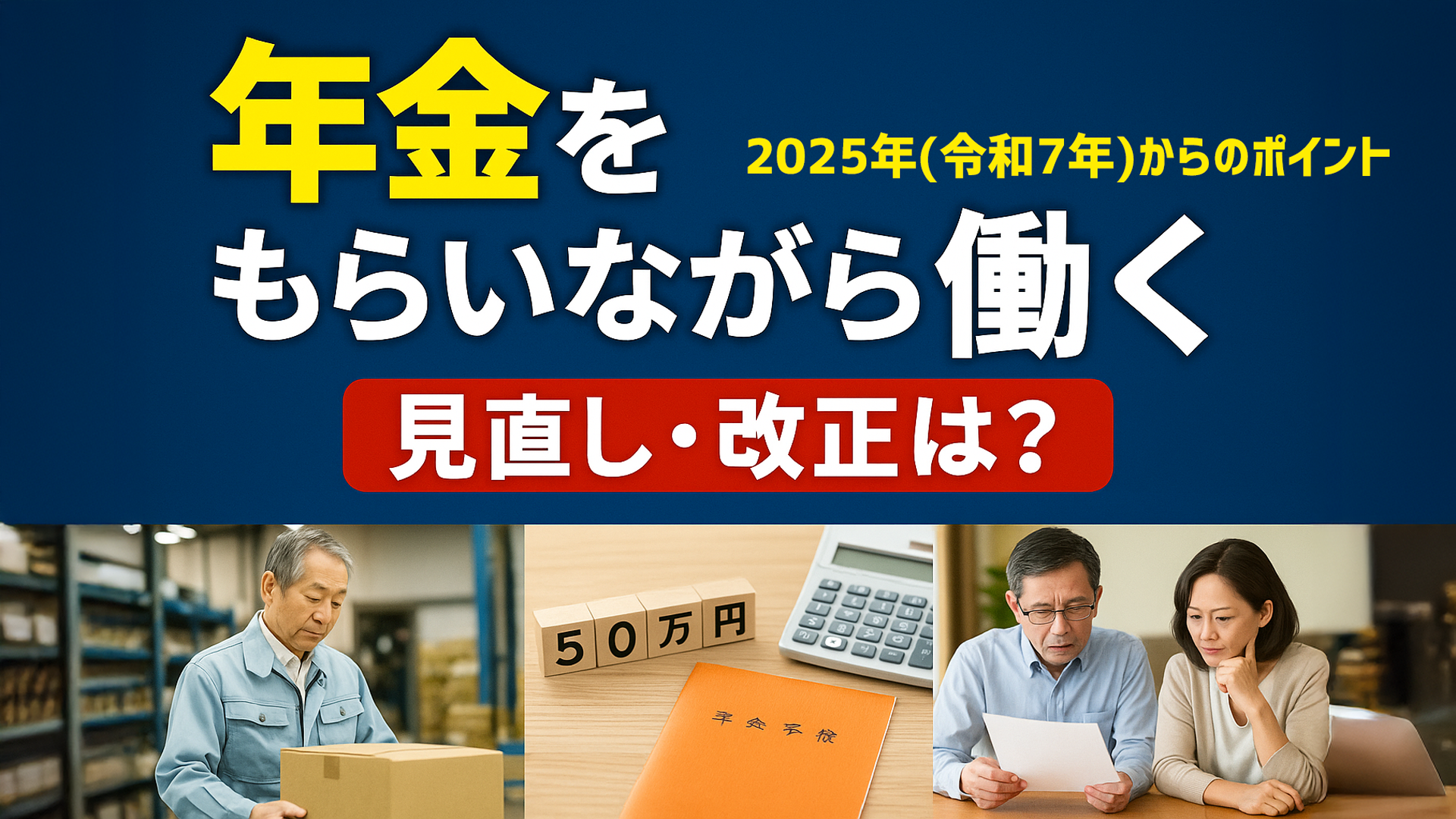「年金をもらいながら、まだまだ元気に働きたい!」
そうお考えのシニアの皆さん、こんにちは。
近年、働き方が多様化し、定年後も活躍される方が増えていますね。しかし、年金や税金の制度は時々見直され、「気づかないうちにルールが変わっていた!」なんてことも。
実は、2025年(令和7年)から、年金をもらいながら働く場合のルールや、所得税の計算に関わる部分で、いくつかの重要な変更が予定されています。
「え?私の年金や税金はどうなるの?」
「働き損にならないか心配…」
「家計の計画を見直した方がいいのかな?」
そんな疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、特にシニアの皆さんに関係の深い2025年からの年金・税金の変更点について、できるだけ分かりやすく解説します。
この記事を読めば、以下の点が分かります。
- 働きながらもらう年金(在職老齢年金)のカット基準はどう変わる可能性があるのか?
- 令和7年から所得税の控除はどう変わる?(基礎控除・給与所得控除)
- 新しくできる「特定親族特別控除」ってどんな制度?
- 扶養に入れる収入の「壁」はどう変わる?(103万円→123万円へ)
- 将来的に、給与と年金の両方をもらう人の税金はどうなる可能性がある?
知らないと損をしてしまう可能性もある大切な情報です。ぜひ最後まで読んで、今後の働き方や家計管理の参考にしてくださいね。
1. 働きながらもらう年金(在職老齢年金)はどうなる?カット基準の見直し
まず、多くの方が気にされているのが「在職老齢年金」の見直しです。
- 在職老齢年金とは?
- 現在の基準額(令和6年度)
- 「働き損」の声と見直しの動き
60歳以上の方が厚生年金に加入しながら(つまり働きながら)老齢厚生年金を受け取る場合、お給料(賃金)と年金の合計額がある一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止される制度です。
現在、お給料(※)と年金額(老齢厚生年金の月額)の合計が月額50万円
(※)正確には「総報酬月額相当額」といい、毎月の賃金(標準報酬月額)+直近1年間の賞与を12で割った額です。
この制度については、「せっかく働いても年金が減るなら、働く時間を調整しよう」と考えてしまう、いわゆる「働き控え」につながるのではないか、という指摘が以前からありました。
そこで現在、この支給停止の基準となる月額50万円を引き上げるか、あるいは制度自体を廃止するか、といった見直しが本格的に検討されています。
政府・与党内では、基準額を「62万円」や「71万円」に引き上げるといった具体的な案も出てきています。
【注意点】カットされた年金は戻ってきません!
この制度でカットされた年金額は、後から支給されることはありません。減額されたら、その分は受け取れないということになります。この点はしっかり覚えておきましょう。
働くシニアが増える中、この在職老齢年金のあり方が、社会の変化に合わせて見直されようとしています。今後の動きに注目が必要です。
2. 税金が変わる!令和7年(2025年)からの主な税制改正点
次にお伝えするのは、税金の変更点です。これは 令和7年(2025年)分の所得税から適用され、多くの方にとっては令和7年の年末調整から影響が出てきます。
主な変更点は以下の3つです。
(1)基礎控除の引き上げ
所得税を計算する際に、全ての納税者の合計所得金額から差し引かれる「基礎控除」。これが引き上げられます。
- 改正後:合計所得金額2,350万円以下の場合、58万円
(現行:合計所得金額2,400万円以下の場合、48万円)
多くの方にとって控除額が増えることになり、減税につながる可能性があります。
(2)給与所得控除の最低額引き上げ
お給料をもらっている方の所得税計算で、給与収入から差し引かれる「給与所得控除」。この最低保証額が引き上げられます。
- 改正後: 最低 65万円
(現行:最低55万円)
こちらも多くの方にとって控除額が増え、減税につながる可能性のある変更です。
(3)新しい控除「特定親族特別控除」の新設
令和7年から「特定親族特別控除(仮称)」という新しい所得控除が始まります。
- 対象となる親族: 生計を一つにする 19歳以上23歳未満の親族(例:大学生のお子さんなど)
- 親族の所得要件:合計所得金額が58万円超 123万円以下であること
(給与収入のみの場合、年収約113万円超 184万円以下に相当) - 控除額: 親族の所得に応じて変動(最大63万円)
これまで、アルバイト収入が多くて扶養に入れられなかった大学生のお子さんなどがいる場合、この新しい控除の対象になる可能性があります。
【注意点】
- この控除を受けるためには、年末調整で専用の申告書が必要になる予定です。
- この制度創設に伴い、源泉徴収税額の計算方法も一部変わる見込みです。
3. 「扶養の壁」も変わる!103万円 → 123万円へ
上記の基礎控除と給与所得控除の引き上げに伴い、所得税がかからなくなる収入の上限、いわゆる「103万円の壁」が「123万円の壁」に変わります。
- 改正後: 給与収入123万円以下であれば、所得税はかかりません。
(基礎控除58万円 + 給与所得控除65万円 = 123万円)
(現行:103万円以下)
これは、パートなどで働く配偶者や、アルバイトをするお子さんなど、ご家族の働き方にも影響する大きな変更点です。
また、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族の合計所得金額の上限も、現行の48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
4. 【将来的な話】給与と年金の両方がある人の控除に上限がつくかも?
最後に、これはまだ決定事項ではなく、将来的な検討事項としてお伝えします。
現在、給与収入と年金収入の両方がある方は、「給与所得控除」と「公的年金等控除」という2つの控除を受けることができます。 これについて、「給与収入だけの人と比べて税負担が軽くなり、公平ではないのでは?」という指摘があります。
そこで、もし「在職老齢年金」の見直しが行われた場合には、という条件付きですが、将来的にこの2つの控除の合計額に上限(キャップ)を設けることが検討されています。 例えば、「合計280万円まで」といった案が出ています。
これが導入されると、特に給与と年金の両方で高収入を得ている方の税負担が増える可能性があります。
💡重要なポイント
これは、収入が増えると手取りが減る「年収の壁」とは異なります。あくまで控除できる額の上限が決まるという話であり、収入が増えれば手取りも増えます。
この控除額のキャップについては、在職老齢年金の議論の結果を踏まえて、令和8年度(2026年度)以降の税制改正で検討される予定であり、まだ決定ではありません。
まとめ:今後の変化に備え、ご自身の状況を確認しましょう
今回は、2025年(令和7年)から予定されている年金・税金の主な変更点について解説しました。
- 在職老齢年金の基準が見直される可能性
- 基礎控除・給与所得控除が引き上げられ、多くの場合で減税に
- 新しい「特定親族特別控除」がスタート
- 扶養に入れる収入の「壁」が103万円から123万円に
- 将来的には、給与と年金の両方がある方の控除合計額に上限が設けられる可能性
制度は常に変化していきます。これらの変更が、ご自身の働き方や収入、ご家族の状況にどのように影響するのか、一度立ち止まって考えてみることが大切です。
今回の情報が、皆さんの今後の生活設計や家計管理のヒントになれば幸いです。
【免責事項】
この記事は、2025年5月時点での情報に基づき作成しています。税制改正の内容は、今後の国会審議等により変更される可能性があります。正確な情報については、国税庁や日本年金機構の公式サイト、または税理士などの専門家にご確認ください。